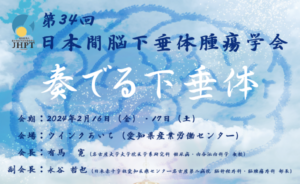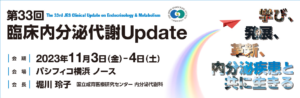2024年6月6日から8日にかけて、神奈川県のパシフィコ横浜ノースで開催された第97回日本内分泌学会学術総会に患者会のブースを出展しました。学会長である慶応義塾大学小児科学教室の長谷川 奉延先生のご厚意により、無償で出展させていただくことができました。
期間中、内科や脳外科の内分泌専門医60名をはじめ、多数の製薬メーカーの方々にブースにお立ち寄りいただき、会の活動についてお話しする機会を得ました。ブースにお越しいただいた先生方や関係者の皆様に、この場を借りて心より御礼申し上げます。
特に当会が実施している、Zoomを用いたオンライン交流会に関して多くのご質問をいただきました。治療内容のみならず、患者同士で復職や日常生活における悩みを共有し、交流会がピアカウンセリングの場として機能している点に感銘を受けたという声も多く寄せられました。ある先生からは「患者の生活の質に目を向け、支えたいという思いを持つ医師が増えたのは、患者会をはじめとする患者さんの活動のおかげです」とのお言葉をいただき、当会としても大変励みとなりました。
これからも、このようなブース出展を通して、今後も当会の活動を広く知っていただき、患者と医師をつなぐ架け橋としての役割を果たしていきたいと思います。
(会員専用ページでは、出展ブースの様子と記念撮影の写真も掲載しています→こちら)